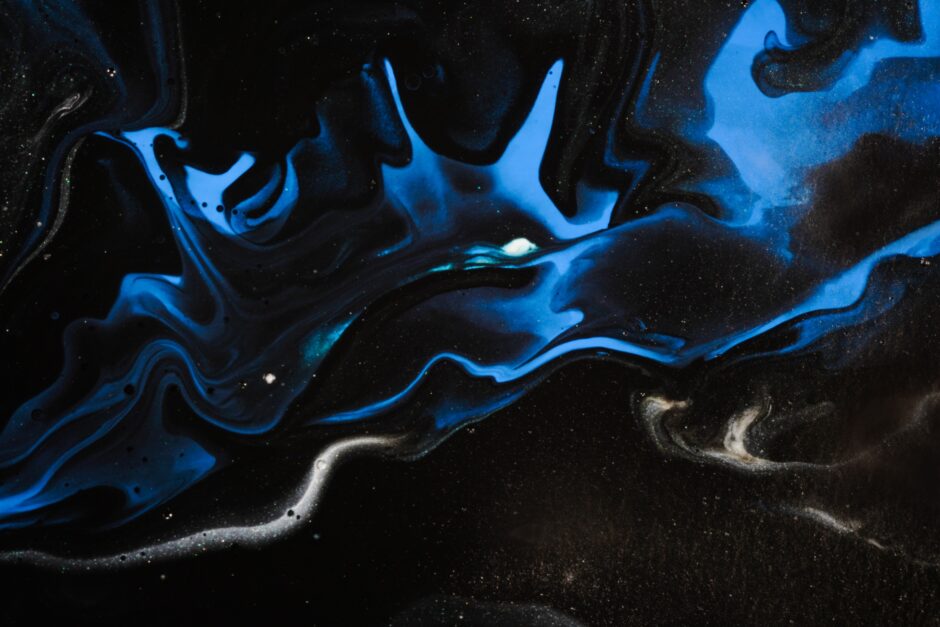ここでは数回に分けて乱流について解説します。
過去には格子法の基本要素について説明しています。ぜひ下記からどうぞ。
乱れのない状態の流れを層流といい、一方で乱れのある流れが乱流と呼ばれます。
現実では振動や外力などの外乱があるため乱れ自体は発生するのですが、粘性力により乱れが減衰することで多くの流れは層流として扱えます。
つまり、粘性が低いと乱流が発生し易いということになり、乱流の発生に関する無次元数としてレイノルズ数Reというものが定義されています。
$$ Re = \frac{UL}{\nu} $$
レイノルズ数は慣性力と粘性力の比で表されます。ここで、代表速度$U$、代表長さ$L$、動粘度$\nu$です。
レイノルズ数が大きくなると(約2300)、層流から乱流に遷移します。この変化点のことを臨界レイノルズ数と呼びます。
ただ、レイノルズ数が大きくても乱れを生じさせなければ乱流は起きにくいです。そのため、流れの代表値はそのままで形状を微調整することで乱流を抑えることができます。
例えば、ゴルフボールのディンプルなどは乱流をうまくコントロールするために凹凸が作られています。
乱流はエネルギー損失の原因となるため、パイプなどの製品では基本的に乱流を抑える設計が行われます。
乱流の平均
乱流は瞬間的に見ると不規則的な流れですが、長時間計測すると特性が見えてきます。
乱流特性を見るため、物理量$\phi$を平均$\bar{\phi}$と変動成分$\phi’$に分解します。
$$ \phi = \bar{\phi} + \phi’ $$
平均$\bar{\phi}$は代表的に3つの計算方法があります。
物理量$\phi$が定常なら、座標rの時間平均$\bar{\phi_t}$は下記式で表されます。
$$ \bar{\phi_t} (r) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int^T_0 \phi (r,t) dt $$
上記が定常流で使われるのに対し、物理量$\phi$が空間的に一様なら、時刻tにおける空間平均$\bar{\phi_s}$は下記式で計算できます。
$$ \bar{\phi_s} (r) = \frac{1}{V} \int_V \phi (r,t) dV $$
最後に、物理量$\phi$が定常でも空間一様でもない場合は、同条件の測定の平均を使うアンサンブル平均$\bar{\phi_e}$が用いられます。
$$ \bar{\phi_e} (r) = \frac{1}{N} \sum^N_{n=1} \phi (r,t)_n $$
アンサンブル平均が最も実用的であり、レイノルズ平均モデルには一般的にアンサンブル平均が使われます。
レイノルズ方程式
非圧縮性の連続の式は下記で書けます。
$$ \nabla \cdot u = 0 $$
また、ナビエ・ストークス方程式は下記となります。
$$\frac {\partial u}{\partial t}+(u \cdot \nabla )u=\frac {1}{\rho} \nabla p + { \nu \nabla^2 u}+{g}$$
これらの四季に対して、レイノルズ分解(流速と圧力を、平均と変動成分に分解)を行います。
$$ u = \bar{u} + u’ $$
$$ p = \bar{p} + p’ $$
すると、次のように書けます。これをレイノルズ式またはレイノルズ平均ナビエ・ストークス方程式(RANS)といいます。
$$\frac{\partial \bar{u_i}}{\partial t} + \frac{\partial \bar{u_i} \bar{u_j}}{\partial x_j} = – \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 \bar{u_i} }{\partial x^2_j} + \bar{G_i} – \frac{\partial \bar{u’_i} \bar{u’_j}}{\partial x_j}$$
ほとんどの項はナビエ・ストークス方程式の項と対応していますが、右辺の最後の項は新しい応力項になっています。
この右辺最後の項のテンソルに$\rho$をかけたものをレイノルズ応力といいます。
$$ \tau_{ij} = \rho \bar{u’_i u’_j} $$
レイノルズ平均ナビエ・ストークス方程式(以下RANS)では、平均圧力や平均流速に加えてレイノルズ応力という未知量が増えました。
この未知量を減らすためにモデル化される、つまり乱流モデルが使用されることになります。
壁関数
壁に最も近い部分では、一般的に粘着条件といわれる流速は壁面速度に等しいという条件が適用されます。
壁最近傍の応力は壁面せん断力$\tau_0$に等しいと考えられるため、下記のようになります。
$$ \tau = \tau_0 = \rho u^{*2} $$
ここで$u^*$は摩擦速度です。
また、壁に最も近い部分である粘性底層では、流速分布は下記の直線分布となります。
$$ \frac{\bar{u}}{u^*} = \frac{u^* y}{\nu} $$
壁よりも十分遠くなってくると、流速分布は下記の対数関数に従うようになります。これを対数則といいます。
$$ \frac{\bar{u}}{u^*} = \frac{1}{\kappa} \ln(\frac{y}{y_0}) + C $$
$y0=\frac{\nu}{u^*}$として長さスケールを定めると、上記の式は次のように表せます。
$$ \frac{\bar{u}}{u^*} = \frac{1}{\kappa} \ln(\frac{u^* y}{\nu}) + As $$
ここで$As$は定数です。
壁に近い部分は粘性底層として直線分布、十分遠いと対数分布を使用しますが、その中間における接続も必要となります。
この領域を遷移層と呼びます。遷移層では直線分布と対数分布をイコールで結んだ下記の式を用います。
$$ \frac{\bar{u}}{u^*} = \frac{1}{\kappa} \ln(\frac{u^* y}{\nu}) + As = \frac{u^* y}{\nu}$$
実験値より$As = 5.5$とわかっているため、$\frac{u^* y}{\nu} = 11.6$となります。これは慣性と粘性の比となっていることから、粘性底層が低レイノルズ数であることを意味しています。
粘性底層、遷移層、対数層は下記で領域分けされます。
- 粘性底層: $\frac{u^* y}{\nu} < 5$
- 遷移層: $5 < \frac{u^* y}{\nu} < 30$
- 対数層: $30 < \frac{u^* y}{\nu}$
渦粘性モデル
乱流のランダム運動により速度が平均化される現象は、粘性として模擬することができます。
乱流による擬似的な粘度増加を渦動粘性係数$\nu_t$として表し、ナビエ・ストークス方程式に組み込むことで乱流渦による影響を考慮した計算が可能となります。
ナビエ・ストークス方程式に組み込む乱流応力$\tau_{ij}$は、渦粘性係数により下記のように書けます。これを渦粘性モデルと呼びます。
$$ \tau_{ij} = \frac{2}{3} k \delta_{ij} – \nu_t ( \frac{\partial \bar{u_i}}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u_j}}{\partial x_i}) $$
ここでkは乱流エネルギーで、乱れの運動エネルギーの平均値です。
渦粘性モデルを用いることで、6つの未知量を含むレイノルズ応力モデルを、渦粘性係数$\nu_t$と乱流エネルギー$k$の2つで表せます。
おわりに
ここでは乱流モデルの基本と壁関数、そしてRANSの基本事項について説明しました。
RANSなど実用的な手法を知る上で土台となる知識なので、ぜひ理解しておきましょう。特に粘性底層と対数層に関しては乱流計算で誤差の出やすい部分なので、気をつけたいところです。
次回は$k-\varepsilon$などよく使われる乱流モデルについて説明します。
 ITとCFD入門サイト
ITとCFD入門サイト